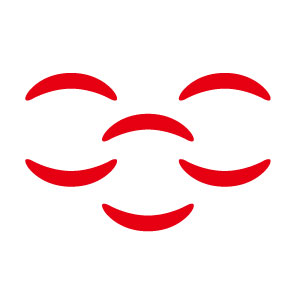派遣可能期間と抵触日の考え方|3年ルールの数え方と実務対応
派遣可能期間と抵触日は、受入れの上限管理に直結する重要テーマです。ここでは、基本の「3年ルール」の数え方、抵触日が近いときの実務対応、例外の考え方をやさしく整理します(概要)。
目次
基本:派遣可能期間の考え方
- 原則、同一の組織単位での受入れは最長3年が目安。
- 期間の起算は、対象の受入れ開始日からカウント。
- 体制・組織の変更でのリセット可否は実態で判断(名称変更のみは原則NG)。
抵触日の数え方(かんたん例)
例:受入開始が2024年11月1日の場合、
抵触日は2027年10月31日(起算日の前日と同日付)とする数え方が一般的です。
- 途中で中断・延長がある場合は、その実態を踏まえてカウントを整理。
- 産休・育休等の代替要員、一定の専門的業務などは取扱いが異なることがあります。
実務対応:抵触日が近づいたら
- スケジュール管理:抵触日の6か月前から受入れ継続の可否・配置転換の検討を開始。
- 情報共有:派遣先との契約更新方針、本人への周知、引継ぎ計画を整備。
- 契約書の整合:期間条項、延長・解除の手続、代替要員の扱いを明確化。
よくあるQ&A
- Q:部署再編で名称が変わったらリセット?
A:実態が同一なら原則リセット不可。業務・指揮命令系統・場所などの実質で判断。 - Q:一時的に受入れを止めた期間はどう数える?
A:取扱いは状況次第。中断の事実関係(契約なし・就業なし等)を記録して整理。